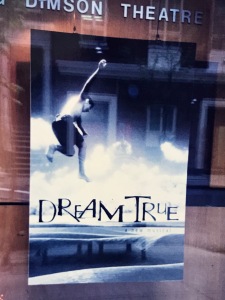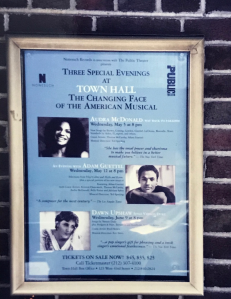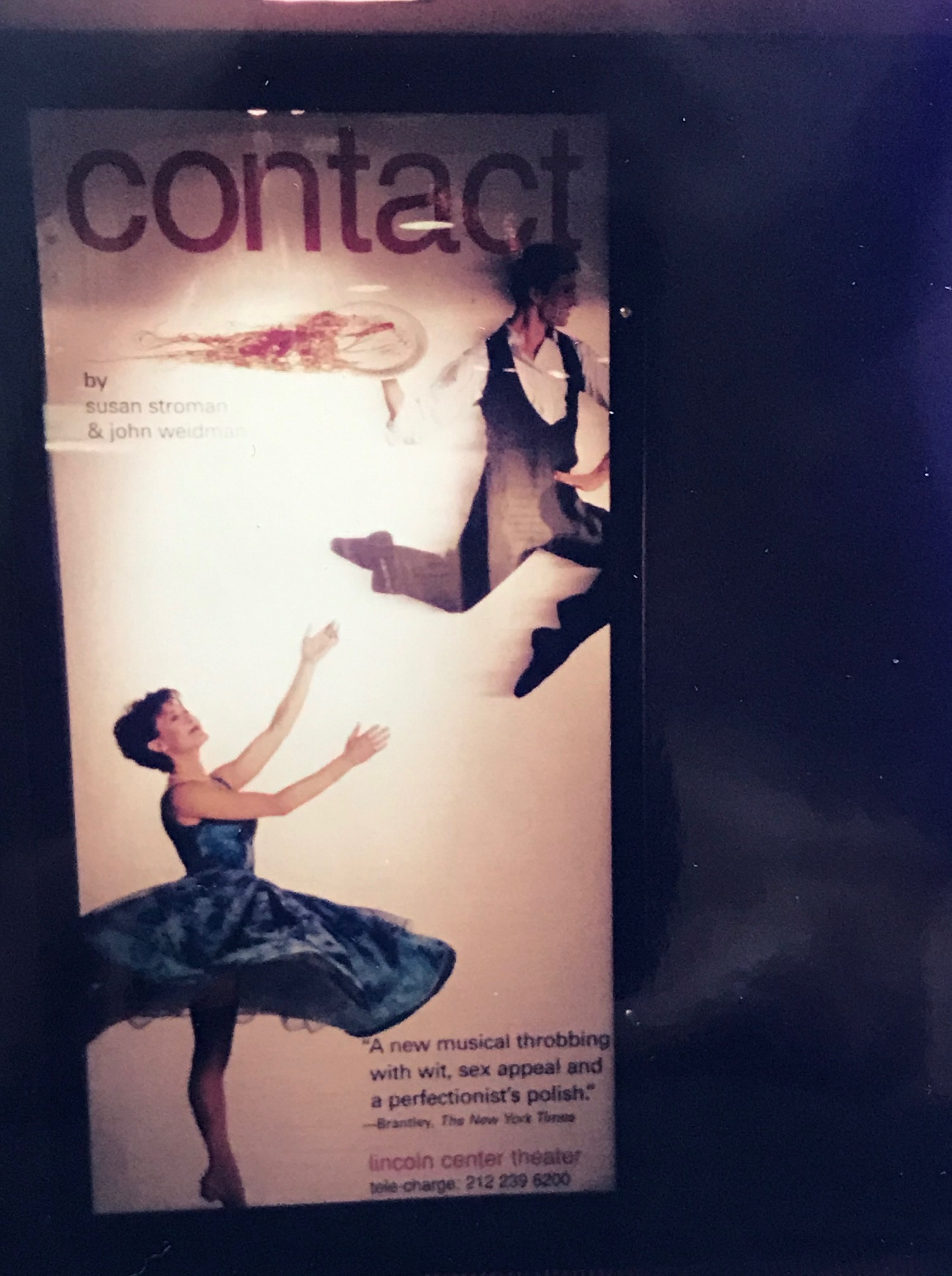『Wonderful Town』(5月7日18:30@City Center)について、「職人技と個人芸が生み出す粋」というタイトルで、4年後のブロードウェイ移行版(2004年1月11日15:00/4月25日15:00@Al Hirschfeld Theatre)を観た後に、まとめて書いた感想。ちょっとくどいです(笑)。
<あまりリヴァイヴァル上演されていない過去のブロードウェイ・ミュージカルをコンサート形式で数回だけ舞台にかける、シティ・センターの春のシリーズ「アンコールズ!」に『Wonderful Town』が登場したのは2000年5月のこと。その舞台で、主演のドナ・マーフィという女優を見直した。
“見直した”などと言っては失礼かもしれない。この時点で彼女は、すでに、トニー賞を2度、ミュージカル主演女優として受賞していたのだから。
しかし、1度目の『Passion』(1994年5月7日観劇)の時は、熱演ではあったものの、異形と言っていいようなメイクで登場し、役柄も常軌を逸していて、とても感情移入できるようなものではなかった。そして、2度目の『The King And I』(1996年5月8日観劇)のイギリス人教師役も、特殊な設定の中で型にはまらざるを得なかった印象だった(この時のトニー賞受賞は『Victor/Victoria』のジュリー・アンドリューズがノミネーションを辞退したためという憶測が根強くあり、授賞式の表情からは、マーフィ自身もそう思っていたように見えた)。そんなこんなで、マーフィと言えば“しんねりむっつり”した役をやる女優だというイメージができあがっていた。
ところが、シティ・センターで観たマーフィは、鉄火肌、とまでは行かないが、実にサバサバしたアメリカ女性を軽やかに演じていたのだ。まあ、考えてみれば、過去の2作で演じた役はどちらもアメリカ人ではなかったわけで(前者がイタリア人、後者がイギリス人)、案外、この役柄あたりが彼女の持ち味に近いのかも、と2000年5月の時点では思い、そうしたマーフィの軽妙な演技と共に、作品自体も、とても楽しんで観た。
そのシティ・センター公演の好評を反映してのことだろう、ドナ・マーフィ版『Wonderful Town』が、若干の衣替えを施してブロードウェイに登場した。その舞台は、派手さや目新しさこそないものの、ミュージカル・コメディの本質的な楽しさ――軽快なドラマから絶妙のタイミングでソング&ダンスに昇華するワクワク感――に満ちている。
ところで、『Wonderful Town』の話の元が『My Sister Eileen』であることはこちらに書いたが、繰り返すと次の通り。
『My Sister Eileen』は、元々はニューヨーカー誌に発表されたルース・マッキニーの短編小説シリーズのタイトルで、その最初の舞台化が1940年にブロードウェイでヒットした同名のストレート・プレイ。そのミュージカル化が1953年にブロードウェイでオープンする『Wonderful Town』。そして、どちらも脚本は、ジョゼフ・フィールズとジェローム・チョードロフ。
『Wonderful Town』は、559公演という当時としてはまずまずのロングランを記録していて、「Ohio」「Conga!」という傑出した楽曲があった(作曲レナード・バーンスタイン、作詞ベティ・コムデン&アドルフ・グリーン)。
バーンスタイン、コムデン&グリーン、そして演出のジョージ・アボット(クレジットなしでジェローム・ロビンズも参加)という顔ぶれは、約10年前の1944年暮れにオープンした『On The Town』と同じ。しかも、どちらもニューヨークを舞台にしていて、タイトルも似ていることから、先行作の成功に乗った続編的な企画だと思われがちだが、そうではない、とスタンリー・グリーンは「BROADWAY MUSICALS Show By Show」で書いている。同書によると、バーンスタインとコムデン&グリーンが参加したのは、リハーサル開始のわずか5週間前だという。
そんな状況だったにもかかわらず、ここまで魅力的な楽曲を書き上げたのは驚き。才人たちの素晴らしい仕事ぶりに脱帽する。
しかし、うまくいった背景には、やはり、『On The Town』と『Wonderful Town』とが似ている、という事実があったのではないか。
『Wonderful Town』の舞台は、1935年のニューヨーク、グリニッチ・ヴィレッジ。そこに2人の若い女性がオハイオから夢を抱いてやって来る。作家志望の姉ルース(こちらがドナ・マーフィ)と女優志望の妹アイリーンのシャーウッド姉妹だ。
田舎から出てきた2人にとって、ニューヨークは目の回るような忙しい街。チャンスをつかもうと行動しても、人波に翻弄されるばかり。おまけに、グリニッチ・ヴィレッジは、おかしな連中でいっぱい。地下鉄の轟音に悩まされる半地下の部屋に住みながら、ルースとアイリーンは、それぞれの夢をかなえることができるのだろうか。
――と、まあ、簡単に言うと、そんな話。
一方、『On The Town』は、入港した“お上りさん”水兵たちが1日だけの休暇をニューヨークで過ごす話(全くの余談だが、初演オープン時、アメリカはまだ日本相手に戦争中。水兵たちはヨーロッパ戦線から帰国したということなのだろうか。ともあれ、この作品のロングラン中に東京大空襲があり、2個の原爆が落とされ、日米は終戦を迎えることになる)。
『On The Town』の印象を、1999年リヴァイヴァル版の観劇記に、こう書いた。
[ストーリーは必ずしも緊密に作られているわけではなく、むしろ、“ニューヨーク観光名所巡り”というコンセプトのスケッチ集という印象。登場人物のキャラクターもそれほど深くは描かれていない。それを、優れたダンス・ナンバーが支える――と言うより、ダンス・ナンバーをスケッチでつないでいくという発想か。]
この、ダンス・ナンバー(=ショウ場面)を“ニューヨーク観光名所巡り”というコンセプトのスケッチでつないでいく、という印象が、『On The Town』と『Wonderful Town』の共通点だ。
もっとも、『Wonderful Town』の場合は、“ニューヨーク観光名所巡り”と言っても、かなり対象を絞り込んで、“’30年代ニューヨーク新風俗巡り”という様相を呈しているのだが、初演の時点で言っても20年近い過去の“新風俗”観て歩きは、時空を超えた“ニューヨーク観光名所巡り”と言えなくもない。
導入部に、ガイドに率いられた観光客の一団が登場して物珍しそうに“流行りのエリア”グリニッチ・ヴィレッジを見て回る、という設定があり、1935年当時の新奇な衣装と立ち居振舞いの住人たちが次々に姿を見せる。その後、シャーウッド姉妹の住むアパートメントの半地下の部屋とその前の通りを中心に、ニューヨークのあちこちで珍事が起こっていく。
で、その背景には、もちろんシャーウッド姉妹の物語がある。メインになるのは作家を志す姉のルースの仕事と恋がうまくいくかどうかという話で、男たちから言い寄られることしきりの妹アイリーン(ジェニファー・ウェストフェルド)をめぐって起こるトラブルが、そこに起伏をつける。そういう物語があることはあるのだが、しかし、構成としては、けっこう“緩め”。と言うか、脇道に逸れる。
例えば第1幕。ルースが出版編集者ベイカー(グレッグ・エデルマン)のオフィスに原稿を持ち込んだ後の場面。一旦はゴミ箱行きにしようとしたルースの原稿を、思い直してベイカーが読むのだが、原稿を読むベイカーの頭の中(観客の目には、ベイカーのデスクの脇)に、ベイカーの同僚編集者2人を共演者として従えたルースが様々な役柄で現れて、ルースの原稿の類型的で馬鹿げた中身を再現する。ここ、ほとんど本筋と関係がない。なにしろ、主眼は、主演女優のおかしな扮装と誇張された動きにあるのだから。
あえて言えば、無理して架空の物語を書こうとしているルースの原稿のひどさを示す場面。さらに深読みすれば、後に結ばれることになるベイカーがルースを強く意識したことを示す場面、ととれなくもない。そういう意味では本筋の伏線になってもいるのだが、でもまあ、印象としては、主演女優がコミカルな持ち味を発揮するためのスケッチ+ショウ場面だ。
もっと本筋と関係ないのが、第1幕最後の「Conga!」の場面。電話で依頼を受けたルースが、来航中のブラジル海軍の取材に向かう。そこでの珍妙なやりとりの中で、なぜかルースがブラジルの水兵たちにコンガの踊りを教えることになる。で、テンポの速いラテンのリズムに乗って、彼らはそのままヴィレッジまでやって来て、街中を踊りの渦に巻き込む。ドラマ的には、騒ぎが起きるという以上の意味は全くと言っていいほど、ない。このエピソードは、陽気でコミカルなダンス・シーンを作り出すためにあると言っても、まず間違いではない。
まあ、ここも、あえて言えば、ルースを引き離しアイリーンをピンチに陥らせる(部屋にやって来た男に迫られる)、という要素もないではないのだが、逆に、意味のない「Conga!」の話に意味を持たせるためにアイリーンの話の方を考えた、という風にも見える。
ちなみに、第2幕にある「Swing」も、タイトルの趣向も含め「Conga!」と同じ発想で作られたショウ・ナンバー。ジャズに乗ろうとしてアタマ打ちでリズムをとるルースに、街の連中がアフター・ビートを教える(このアイディア、タイトルも同じ『Swing!』のローラ・ベナンティのナンバーでも使われてましたね)のをきっかけに、やはり街中が踊りの渦となる。これ、「Conga!」以上にドラマとは関係のない、ショウ場面のためのだけに存在するエピソードだ。
――というわけで、『Wonderful Town』は、『On The Town』同様、一応ドラマのストーリーは持ちながらも、ショウ場面を“ニューヨーク観光名所巡り”というコンセプトのスケッチでつないでいく、という印象の作品になっているのだ。
で、話を戻すと、そういう、ショウ場面主体に構成されているミュージカルだからこそ、バーンスタインとコムデン&グリーンは、短期間の内に的確な仕事をすることができたのではないだろうか。おおよそのドラマの流れの中に、まずはショウ場面を設定していって、ドラマの流れではなくショウ場面のバランス主体に考えて楽曲を書いていく。「Conga!」や「Swing」が登場する背景には、そんな風な創作過程があったように思えてならない。
そして、もちろん、そんな「Conga!」や「Swing」といった際立ったダンス・ナンバーを生み出すこと自体に、バーンスタインとコムデン&グリーンの楽曲作者としての才能が表れているのだが、彼らのミュージカルの達人としての“技”が本当に発揮されているのは、シャーウッド姉妹が新しい部屋に落ち着いてすぐに歌われる楽曲、「Ohio」においてだ。
「Ohio」は、到着初日からニューヨークに翻弄された姉妹が故郷を思って歌う、のんびりしたテンポのユーモラスなナンバーで、幕開きから間もない時点で登場して、『Wonderful Town』が“とぼけた”調子の作品であることを知らしめる。と同時に、性格の違う姉妹の互いに対する愛情や、都会にやって来た“田舎者”の心情を、笑いにくるみつつ、でも、しっとりと温かく表わす。
この楽曲が、汚く狭い半地下の部屋で肩を寄せ合うシャーウッド姉妹によって歌われることで、観客は、作品世界に惹き込まれ、すっかり主人公たちに感情移入してしまう。この時点で、作品は半ば成功していると言っていい。実に、うまい。
こうした重要なポイントに、一見地味でありながら、実は印象的なメロディを持つ、ドラマ上も深い意味のあるナンバーを提出できる。そうしたことこそがミュージカルの楽曲作者に求められる能力であり、このような楽曲が時として脚本以上に大きな意味を持つから、ミュージカルにおいては誰よりも楽曲作者が先にクレジットされることになるのだ。
『Wonderful Town』の楽しさの 1つは、そうしたスタッフの熟練の“技”を味わえるところにある。
さて、話はさらに戻って、ドナ・マーフィ。
“緩い”ドラマでつながったショウ場面主体のミュージカルの中で、これまで観た作品では(どちらかと言えばショウと言うよりも)ドラマ寄りに演技していたドナ・マーフィが、意外なほど軽快に、歌い、そして踊る(ま、踊りは、ブロードウェイのレヴェルとしてはほどほどだが、体力的にはかなり動き、果てにダイヴも見せるのには驚いた)。しかも、それがサマになっていて、充分な存在感を示し、舞台を支える。その見事なミュージカル・コメディエンヌぶりは、2001年リヴァイヴァル版『Bells Are Ringing』のフェイス・プリンスと肩を並べると言ってもいい(ちなみに、『Wonderful Town』と、その3年後に初演の幕を開けた『Bells Are Ringing』には、コムデン&グリーンやジェローム・ロビンズが参加していたり、舞台がダウンタウンの半地下部屋だったりと、共通項が多い)。
そんなマーフィの“芸”が、スタッフの“技”とあいまって、イキイキとした形で観られる。それが『Wonderful Town』のもう1つの楽しさだ。
――と、大活躍を大いに認めた上で、今回観直して、ドナ・マーフィの“芸”について気づいたことがある。「彼女の持ち味に近いのかも」と4年前にシティ・センターで観た時には思ったマーフィのルース役だが、今回は、そう思わせるのも彼女の演技力なのかも、という風に感じたのだ。
どういうことかと言うと、「Conga!」だの「Swing」だのといったジャズ/ラテン系のナンバーのビートに、マーフィの歌は必ずしもノリきっていなかった。微妙なニュアンスなのだが、グルーヴが生まれるところまで行っていない。例えば、『Swing!』のアン・ハンプトン・キャラウェイのような“本職”と比べた場合、ということだが。
だから、マーフィの人間性は知らないが(もしかしたら本当にルースみたいな人なのかもしれないが)、歌い手としては、好きでビートのあるナンバーを歌い込んできた、というような人ではないのだと思う。むしろ、どんな役でも達者にこなしていくオールラウンドなミュージカル女優なのだろう。それはそれで素晴らしい。どちらにしても、この舞台がマーフィの“芸”によって成り立っているのは間違いないのだから。
初演の舞台がどんなだったかを知らないので今回のリヴァイヴァルがどこまでその影響下にあるのかわからないが、演出も兼ねたキャスリーン・マーシャルの振付は、“ほどよい”冴えを見せ、ウキウキさせてくれる。
“ほどよい”というのは、凝りすぎずに軽快なエンターテインメントの範囲内で鮮やかに見せている、というような意味。例えば、導入部の“流行りのエリア”グリニッチ・ヴィレッジ観光のシーンなど、モダン・バレエ的手法を使いつつも、わかりやすくユーモラスにまとめている。
こうした“ほどよい”感じで全てが統一されているのが『Wonderful Town』の粋なところだ。
後ろ半分にオーケストラを配するために舞台の前半分しか使えないという「アンコールズ!」の限られた条件を逆手にとって、袖から袖へと横に延びる橋状の通路と、そこから舞台に下りる短い階段を基本に、シンプルだが意匠を凝らした背景を上下に動かすことで様々な場所を表現した優れたアイディアの装置は、ジョン・リー・ビーティ。ブロードウェイの劇場に移しても、そのアイディアは、安っぽくならず、充分に生きた。
繰り返すが、主演ドナ・マーフィの“芸”と楽曲作者バーンスタインとコムデン&グリーンの“技”は見事。
ことに、ブロードウェイに移っての今回の再見再々見では、楽曲の細かいアイディアを再確認。メロディの一部を共有しながら楽曲同士が有機的に結びついて、楽曲でしか表現できない感情やユーモアを描き出す。これがミュージカルってもんだろう。
今のブロードウェイで最もブロードウェイらしいミュージカル・コメディは何かと訊かれたら、迷わず『Wonderful Town』だと答える。>
[追記]
脚本補作デイヴィッド・アイヴズ。