★2005年4月@ニューヨーク(その5)
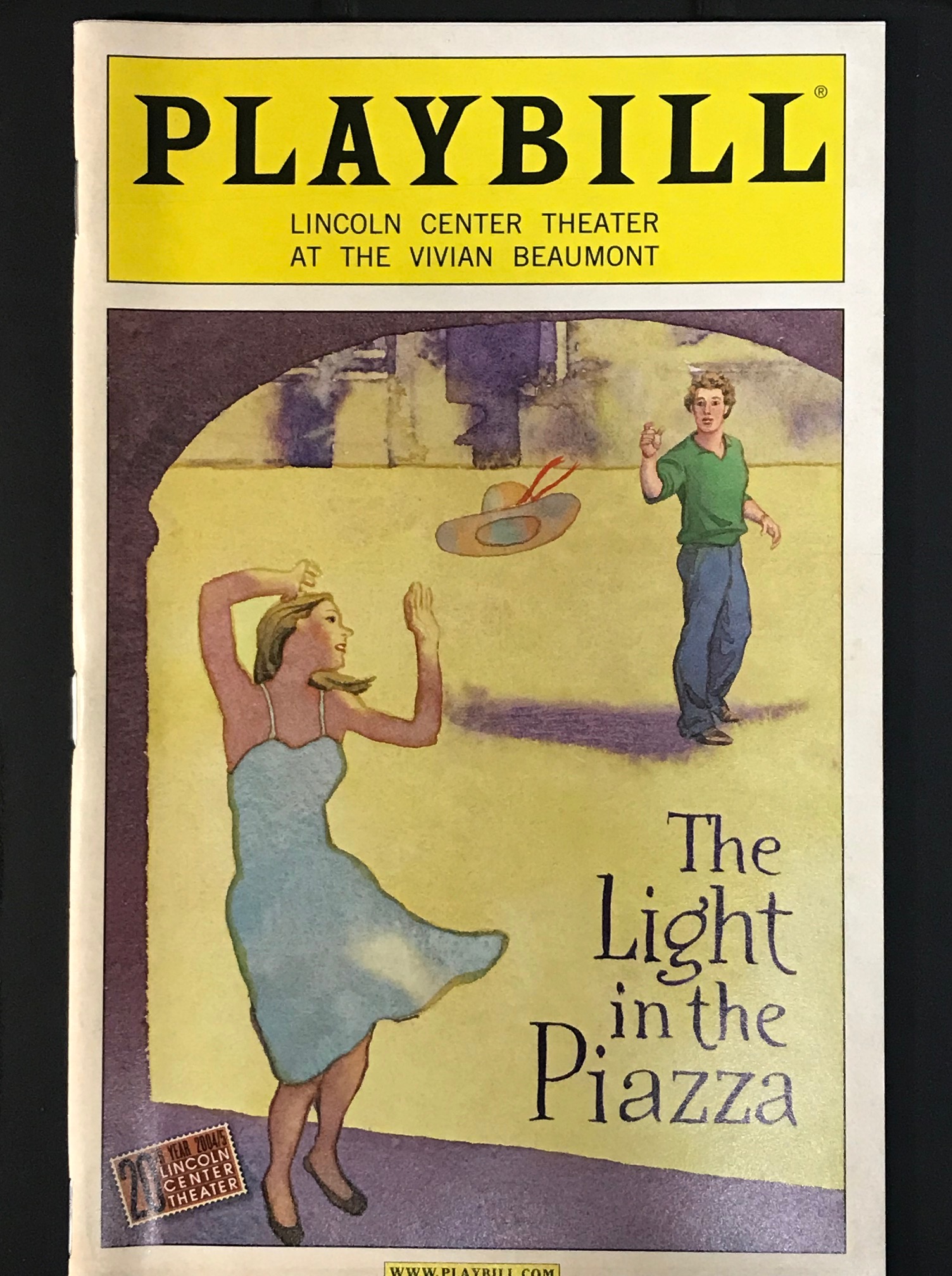
『The Light In The Piazza』(4月15日20:00@Vivian Beaumont Theater)についての観劇直後の感想は次の通り(<>内)。
<“期待の”楽曲作者アダム・ゲテールの初のブロードウェイ作品(と言っても劇場の場所はリンカーン・センターだが)。
イタリアを訪れたアメリカ人母娘の物語で、映画『Summertime』(邦題:旅情)/舞台ミュージカル化タイトル『Do I Hear A Waltz?』(邦題:ワルツが聞こえる?)の変奏かと思いきや、意外な展開に。
善人ばかりだが孤独を抱えた人々のシリアスなドラマを、コミカルさを交えた絶妙なタッチで描く。そこにゲテールの豊かな楽曲が絡んで、心に沁みる仕上がり。
イタリア人役がイタリア語でしゃべり、歌うという趣向に驚いたが、それも実に効果的だった。>
この時点では、ゲテールがメアリー・ロジャーズの息子、リチャード・ロジャーズの孫であることを知らない。したがって、『Do I Hear A Waltz?』とゲテールとの縁についても気づいていない。この件については、最近、無料配信音楽誌「ERIS」32号で「ロジャーズからソンドハイム経由ゲテールへ」というタイトルで掘り下げてみました。けっこう面白い話だと思う。
『The Light In The Piazza』については2019年のロンドン公演の感想を先にアップしてある。そこでは主に、主演したルネ・フレミングが同公演に先行して出したアルバム『Broadway』の中で歌っている、同作のナンバー「Fable」について書いていて、作品そのものについてはあまり触れていない……気がしていたが、なんと、「肝」になる部分を書いてあった(笑)。次の通り(ちなみに、プレイビルに書いてある設定は1953年の夏)。
子供の頃の事故が元で精神的な成長が止まっている26歳の娘クララ。彼女を連れてハネムーンの地フィレンツェを訪れた中年のアメリカ人女性マーガレット。
対人関係で発作的に混乱してしまう娘を慮(おもんばか)って、なるべく他人に近づけないようにしていたにもかかわらず、クララはイタリア人青年と恋に落ちる。誰にも事情を打ち明けられないマーガレットだが、青年の家族にも馴染んでいくクララを見て、娘は自分の庇護から解き放たれるべき時が来たのかもしれないと思い、2人の結婚を祝福する決心をする。
さらに、テーマとして「浮かび上がるのは女性の自立→個人の尊厳」とも書いてある。
原作は1960年発表のエリザベス・スペンサーの同名小説。
おそらくヒット小説だったのだろう、1962年にアーサー・フリード製作、オリヴィエ・デ・ハヴィランド主演(母役)でMGMで映画化されている。監督ガイ・グリーン。そちらは、イタリア・ロケやロッサノ・ブラッツィが主要な役で出ていることも含め、前述の映画『Summertime』の二番煎じ感濃厚。
先の「ERIS」の原稿にも書いたことだが、この作品のミュージカル化のきっかけは、ゲテールの母メアリー・ロジャーズが1960年代に原作小説を読み映画版を観た上で父リチャード・ロジャーズにミュージカル化を勧めるが、リチャードが乗らなかったので、30年後に息子のアダムに勧めた、ということであったらしい。
アダム・ゲテールの楽曲はもちろん、ゲテールと共に編曲を手がけ、音楽監督も務めているテッド・スパーリングの仕事も含めて、とにかく音楽が素晴らしい(追加編曲ブルース・コフリン)。
クレイグ・ルーカスの脚本も優れている。英語とイタリア語混交のセリフをうまく処理したこともあるが、主演であり、かつクララの秘密を抱えるマーガレット役に、狂言回しと言うか観客に向けてのナレーターの役割もやらせたのが大きい。繊細な内容の今作がユーモラスな空気を醸し出しながら成功した要因のひとつが、そのアイディアだと思う。その分、マーガレット役者の負担は大きくなった。ヴィクトリア・クラークのトニー賞受賞は当然だろう。
そのヴィクトリア・クラーク、これ以前にも重要な役どころを演じているのを観ているのだが(例えば『How To Succeed In Business Without Really Trying』のスミッティ役とか『Titanic』の乗客とか)、役は印象に残っていても、役者としての彼女は印象に残っていない。脇に回ってうまく、押し出しは強くない、そういう役者なのだろう。この後も活躍しているが、彼女のよさがピタリとハマった、これが一世一代の当たり役だったのだと思う。
その他の役者について。
クララ役はケリ・オハラ。『Sweet Smell Of Success』の感想で書いているが、同作での“病的にまで繊細”な感じをこの作品でも引き継いでいて、それが彼女の初期の印象を決定づけたと思う。逆に言うと、クララが実に適役に思えた。が、実は彼女、ブロードウェイ公演に先立つ2003年のシアトルや2004年のシカゴでの試演では、クララではなく、イタリア人青年の身内の1人を演じていたという。その時のクララ役は、『The 25th Annual Putnam County Spelling Bee』で注目を浴びるセリア・キーナン=ボルジャー。確かに彼女がクララでも不思議はない。が、当然のことながら、いくぶんニュアンスの違う舞台にはなっただろう。このあたりの巡り合わせは紙一重か。
イタリア人青年(ファブリツィオ)役のマシュー・モリソンはブロードウェイ版からの参加。試演で演じていたスティーヴン・パスクァール(『A Man of No Importance』)がTVシリーズ出演で抜けたために急遽行なわれたオーディションを受けたのだとか。今年(2021年)の1月末に『The Light In The Piazza』主要オリジナル・キャストのリモートによる座談会が行なわれ、オンラインで公開されたのだが、そこでモリソンが苦笑いしながら言っていたのが、他のキャストが自分のことを“ヘアスプレイ・ガイ”として見ていた、ということ。『Footloose』『The Rocky Horror Show』に途中参加した後に『Hairspray』でオリジナル・キャストになったモリソンは、別路線の新境地を目指してこの作品に参加したのだが、やはり最初は色物扱いされている感があったということらしい。
マーガレットとのやりとりで物語上重要な役割を果たすことになるファブリツィオの父親を演じたマーク・ハレリックは『Hank Williams: Lost Highway』の脚本家の1人だった人。軽妙かつ渋く好演。
ファブリツィオの兄役が、名ダンサー、マイケル・ベレッセ(リヴァイヴァル『Chicago』他)。ファブリツィオをからかって一瞬見せる踊りが素晴らしい。ほぼ全編イタリア語。
その妻役がサラ・ウリアーテ・ベリー。この作品の前は『Taboo』に出ていた。ケリ・オハラが試演で演じていたのはこの役なのだろうか。どうもイメージが湧かないのだが。
演出はバートレット・シェール。これがブロードウェイ・デビュー。振付はジョナサン・バタレル 。
素晴らしい装置は、バートレット・シェール作品とは切っても切れないマイケル・イヤーガン。クリストファー・アカリンドの照明も見事だった。

“The Chronicle of Broadway and me #399(The Light In The Piazza)” への34件のフィードバック