★2003年10月~11月@ニューヨーク(その2)/★2004年1月@ニューヨーク(その2)
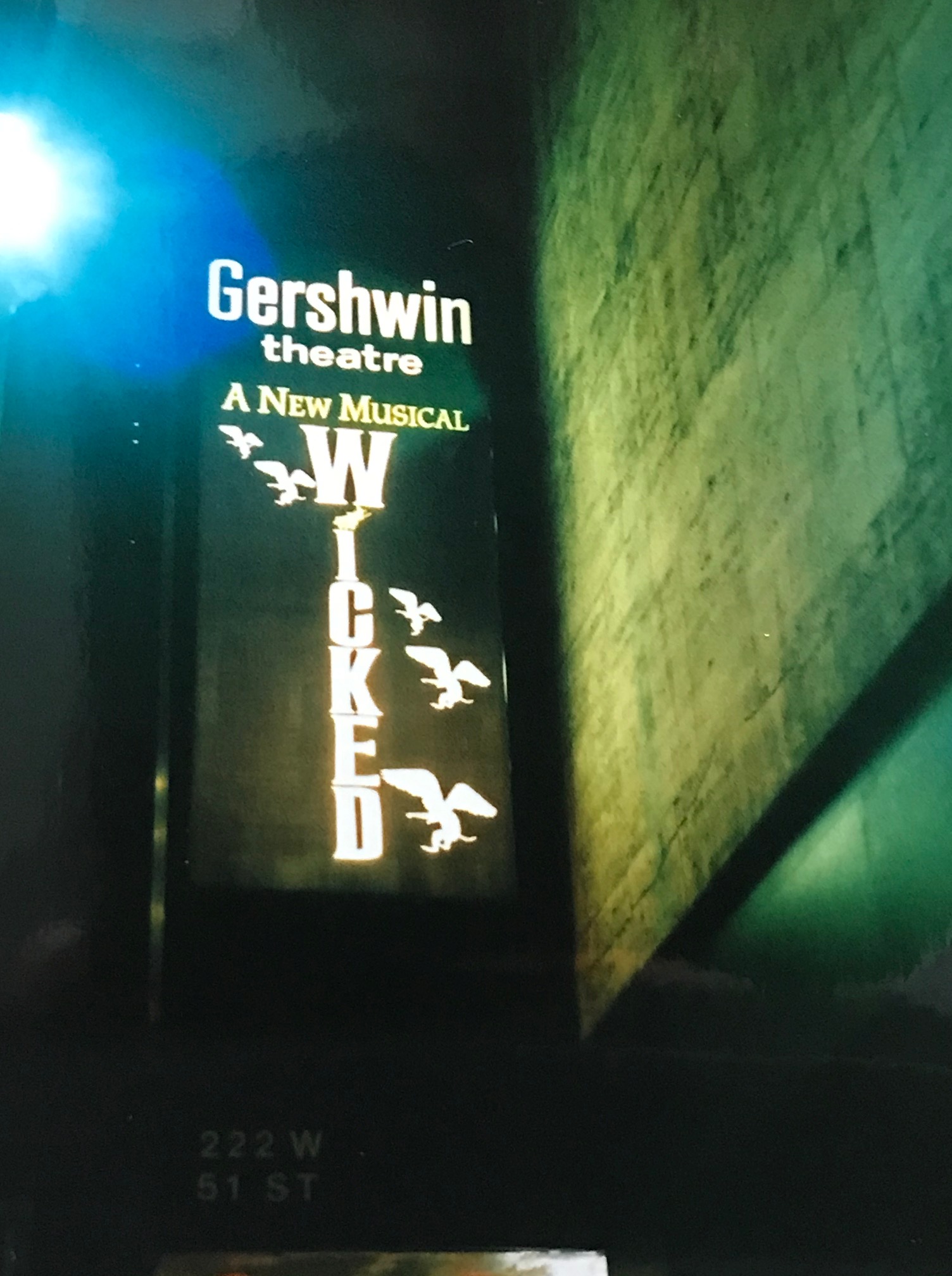

『Wicked』(10月30日18:30@Gershwin Theatre)については、この回と、翌2004年1月8日20:00の2度の観劇を経て、「ドロシーの知らないオズ世界」というタイトルで旧サイトに感想を書いている(書いたのは2004年1月13日)。
大ヒット作に対して、最終的には褒めているが、けっこう辛口。スティーヴン・シュウォーツのオーソドックスな楽曲を物足りなく感じたんだと思う 。
以下、<>内が当時の感想 。
<極言すれば、クリスティン・チェノウェスに尽きる。
キャスト、スタッフ、そして装置、照明、衣装、と、豪華に揃えた『Wicked』は、もちろんそれなりの仕上がりにはなっていて、華やかさもあり、観客は大いに盛り上がっていたが、つぶさに観ていけば、この作品がチェノウェスの魅力なしにはありえなかったことは明白だ。
と言うのは――。
①楽曲に魅力が足りない。
『Godspell』で知られるスティーヴン・シュウォーツ(作曲・作詞)の書いた楽曲は、チェノウェスに当て書きしたに違いない「Popular」という1曲を除くと、観終わった後まで印象に残るものがほとんどない。その「Popular」にしても、チェノウェスの個性と歌唱力におんぶした格好。リヴァイヴァル版『You’re A Good Man, Charlie Brown』でチェノウェスのトニー賞受賞を決定づけたナンバー「My New Philosophy」のように、彼女の魅力を見事に引き出しているというわけではない。
チェノウェスに限らず、主役級の役者(イディナ・メンゼルやジョエル・グレイ)の歌う楽曲の多くは、明らかに当て書きしてあって、その姿勢は間違ってはいないのだが、その分、役者たちが過去に歌った印象的なナンバーと比較して聴かれるのは避けられない。強いオリジナリティが要求されるゆえんだが、その辺が弱かった。メンゼルのパワフルな声を生かそうとした、歌い上げることの多いナンバーは、どうしても『Rent』での熱唱を思い起こさせるし、グレイの歌うヴォードヴィル調のナンバー(「Wonderful」など、悪くはないのだが)も、何か他のミュージカルでグレイが歌っていた楽曲のように思えてしまう。総じて、二番煎じに聴こえるという難があるのだ。
楽曲の魅力の足りなさ。これはミュージカルにとっては、かなり痛い。
②『The Wizard Of Oz』にこだわりすぎている(余談だが、同映画の原作小説のタイトルは『The Wonderful Wizard Of Oz』。だから、魔法使い役グレイの持ち歌が「Wonderful」なのではないだろうか)。
『Wicked』は、隅から隅まで『The Wizard Of Oz』の裏話としてでき上がっている。極端に言うと、『The Wizard Of Oz』によって補完される、不完全な物語なのだ。まあ、原作小説『Wicked』がそうだから致し方ないのではあるが、そういう意味では、一定の予備知識を必要とする、ある種マニアックな作品だと言っても間違いではない。
しかし、多くのアメリカ人、ことにミュージカルの劇場へ足を運ぶようなアメリカ人にとっては、年齢に関係なく、『The Wizard Of Oz』の世界、とりわけ1939年製作のジュディ・ガーランド主演映画版は血肉化した“常識”のようなものだろうから、『The Wizard Of Oz』との呼応関係は、必ずしも観劇の妨げにはならないのかもしれない。むしろ、それが呼び水になると製作者が踏んだがゆえの舞台ミュージカル化、とも考えられる。
ではあるかもしれないが、ほとんどの登場人物のみならず登場動物に到るまで、その運命について、『The Wizard Of Oz』との整合性を細かく描いていくために、この作品が独自に持つテーマ(異端者に対する社会からの抑圧の告発)の印象が薄れる結果となったのは事実。まあ、観ている側からすれば、そうしたテーマなどない徹底したパロディであっても別にかまわないのだが、結果としては、どっちつかず。欲張りすぎて、とっちらかった印象になったのは否めない。
楽曲が決め手に欠け、盛り込みすぎの脚本(ウィニー・ホルズマン)が焦点を絞りきれていない。となれば、いくら大がかりな装置を準備したとしても見どころのはっきりしない失敗作になっておかしくないのだが、それを支えて、とにもかくにも見栄えのするミュージカルにまとめ上げたのが、チェノウェスの歌と演技とスターのオーラ。
久々にブロードウェイに登場した彼女の晴れ姿を拝むためだけに観ても損はない。少し厳しい言い方だが、それが『Wicked』だ。
これからストーリーを長々と(それでも端折りながら)書きますが、『The Wizard Of Oz』との関係については説明しないので、各自ヴィデオででも確認してください(このサイトの読者のみなさんには無用の断りかもしれませんが)。また、完全にネタばれですので(この作品の場合、楽しみが半減するかも)、その点もご注意を。
物語は“悪い(wicked)西の魔女”が溶けて死んだところから始まる。後に残るのは黒いトンガリ帽だけ。主人を失って散っていく空飛ぶサルたち。“よい魔女”グリンダ(クリスティン・チェノウェス)が現れ、オズの国の住人たちと共に“悪い西の魔女”の死を祝う。めでたしめでたし。――ってことで退場しようとするグリンダに質問が飛ぶ。
“悪い西の魔女”と友達だったってホント?
その質問を曖昧に肯定してグリンダが始める回想は、なぜ“悪い西の魔女”が“悪い魔女”になったか、という話。そして、“悪い西の魔女”になる少女エルファバ(イディナ・メンゼル)と、“よい魔女”グリンダになる少女“ガ”リンダ(もちろんチェノウェス)の紆余曲折する友情の話。
マンチキンランド(オズの一地方)の領主の第一子であるエルファバは、父に隠れた母親の不倫によって生まれた、緑色の肌の持ち主。と同時に、感情が昂ぶった時に発揮される強力な魔力の持ち主でもあった。肌の色故に周りの人々のみならず父親からも疎まれ、疎まれるが故に、強力な魔力で時折周囲を驚かせ、結果さらに疎まれる、そんな少女だ。
エルファバは家を離れ全寮制の学校に入学するが、それは足の不自由な妹ネサローズの面倒を見るため。しかし、そこで、明るく華やかな、そして実はちょっと計算高いブロンドの髪の少女ガリンダに出会って、運命が変わっていく。
思惑違いでルームメイトにされたエルファバとガリンダは、互いに心の中で嫌い合っているが、ダンス・パーティで起こった事件をきっかけに心を通わせ合うようになる。
そんな折、エルファバが心を開いていたヤギの教師ディラモンドが学校を去ることになる。実は、オズの国では動物たちが人間と同じように2本足で歩き話すこともできる。それを嫌う人間が、動物から言葉を奪い、収監しようとしているのだ。ヤギの教師も彼らに連れ去られる。それに怒ったエルファバは、虐待される実験用の仔ライオンを連れて逃げる(虐待の後遺症でライオンは臆病に育つ)。その時に一緒に逃げてくれるのが、ガリンダのボーイフレンド、フィエーロ。以降、2人は心の奥で惹かれ合うようになる。
探しに来た校長のモリブル夫人がエルファバに手渡したのは、魔法使いが送ってきた招待状。入学した時からエルファバの魔力を高く評価していた夫人が、頼んでくれていたものだ。魔法使いの力をもってすれば動物たちを救える、と喜ぶエルファバは、見送りに来たガリンダも誘い、希望に満ちてエメラルド・シティに向かう。この時、ガリンダは自らグリンダと改名。ヤギの教師がいつも間違ってそう呼んでいたからだ。
魔法使い(ジョエル・グレイ)は、いつも国民を脅えさせるために使う大きな機械仕かけを使わないで面会してくれる。そこに、モリブル夫人が現れ、実は魔法使いの広報秘書でもあるのだと名乗る。魔法の書をエルファバに与え、試しに執事の猿を飛べるようにしてみてくれと言う魔法使い。言われるままにエルファバが呪文を唱えると、猿の背に羽根が生える。それも、魔法使いが捕らえていた全ての猿の背に。それを見た魔法使いとモリブル夫人は、これで猿たちをスパイにして敵情を探ることができると喜ぶ。モリブル夫人は、実は魔力などない魔法使いに貢献させるつもりで、エルファバに目をつけていたのだった。
“敵”などという発想に嫌悪を抱き、魔法使いに頼んでも世界がよくならないことに愕然としたエルファバは、魔法の書を持って逃げる。とりなそうとするグリンダだが、エルファバの決意を知り、彼女の気持ちを支持する。自分の秘密を知られすぎた、と、エルファバを捕らえる命令を下す魔法使い。エルファバは魔法で不幸を生む、と国民に喧伝するモリブル夫人。かくしてエルファバは、“悪い西の魔女”に仕立て上げられる。(第1幕終わり)
しばらく後。
モリブル夫人の下でやむなく情宣活動をすることになってしまっているグリンダは、オズの国の人々に向かって(エヴィータのように)、“悪い魔女”は去った、と平穏を告げている。その傍らには、オズの兵士の長になったフィエーロがいて、2人は婚約することになっているが、実はフィエーロはエルファバのことが気になってしかたがない。
その頃エルファバは、すでに学校を出たネサローズの住む実家に現れる(「There’s no place like home」というエルファバ)。父が失意の内に亡くなったことを告げられたエルファバは、2人きりの家族になったのね、と親愛の情を示すが、家族の不幸は全て“悪い魔女”になった姉のせいだと信じているネサローズに拒絶される。そうではないことを示すため、魔法でネサローズの足を直すが、そのおかげで、これまで付きっきりで世話をしてくれていたボウクが、ネサローズの元を去ると言い出す(実はボウクは憧れていた“ガ”リンダにそそのかされてネサローズに付き添ってきた)。取り乱したネサローズは、エルファバの魔法の書の呪文を唱えてボウクの心(臓)を消す。後悔するネサローズに頼まれ、ボウクを救うエルファバ。だが、魔力が足りず、命を取り留めたボウクの姿はブリキ男に変わっていた。
次に魔法使いのところに現れたエルファバは、檻に入れられた空飛ぶ猿たちを解放してほしいと要求。魔法使いはそれに応えるが、同時に、やはり囚われていたディラモンドが、すっかり言葉を奪われた状態で現れたのを見て、一瞬喜んでいたエルファバの怒りが再び燃え上がる。そこにやって来るのが、兵士を引き連れて魔法使いを警護するフィエーロ。相手がエルファバなのを知ったフィエーロは、命令して兵士を去らせ、エルファバと共に逃げる。
2人きりになり、素直に互いの想いを確かめ合うエルファバとフィエーロ。ところが、エルファバに悪い予感が。妹が危ない。空から家が降ってくる……。
予感は的中。マンチキンランドでは、竜巻に飛ばされてきたあばら家の下敷きになって、ネサローズは死んでしまっていた。その傍らで、黄色のレンガ道を去っていく“誰か”に優しげに声をかけて見送るグリンダ。駆けつけて事態を知り、嘆くエルファバは、死んだ者の靴まで奪って、と怒る。どうやら、“誰か”はネサローズの赤い靴を履いていったらしい。そこに、またしても兵士たちが。今度は端(はな)からエルファバを救うために現れるフィエーロ。だが、エルファバは逃れたものの、フィエーロは捕らえられ、処刑されることになる。
クライマックスは古い城。絶望したエルファバは、魔法の書をグリンダに託し、捕らえていた“誰か”に“水”をかけられて、この世から姿を消すことを選ぶ。“悪い西の魔女”の体は溶けてゆき、トンガリ帽だけが残る。最初のシーンに戻ったわけだ。
さて、あとは後日談。エルファバが大切にしていた母の形見のビンが、魔法使いが持っているビンと同じであることから、2人が父娘であることを知ったグリンダは、魔法使いにそのことを告げて後悔させ、“よい魔女”の権威で国外追放を命じる(気球で)。そして、悪の元凶とも言えるモリブル夫人を収監する。
“悪い西の魔女”の死を祝うオズの国の住人たちと“よい魔女”。その陰で、魔女の城を訪れる者がある。エルファバの魔法で生き返ったフィエーロだ。ただし、魔力の限界からカカシとして。彼が“悪い西の魔女”が溶けたあたりの床をノックすると、隠し扉が開いてエルファバが出てくる。手を取り合いオズの国を去る2人。
全ては、エルファバとグリンダだけが知る秘密の物語だった。
――と、こうして『Wicked』のストーリーを説明しようとすると、自然にエルファバが中心になっていく。当然のことだ。主人公は“悪い(wicked)魔女”エルファバなのだから。でもって、グリンダ(ガリンダ)は、その周りをウロウロする脇役でしかなくなってしまう。
にもかかわらず、グリンダ(ガリンダ)がエルファバと並ぶ主役の1人になったのは、なぜか。言い方を変えると、メンゼルと並んでチェノウェスをキャスティングするほど重要な役となっているのは、なぜか。
この感想の最初の方で、『Wicked』のテーマを「異端者に対する社会からの抑圧の告発」と書いたが、今のアメリカ(ことにジョージ・ブッシュ周辺)の風潮を背景にしたように感じられるこのテーマの、“異端者”というのは、この物語の中では、もちろんエルファバのこと。では、グリンダ(ガリンダ)は何なのかと言うと、“異端者”を抑圧する社会に属する“善良なる市民”、ということになるだろう。
“善良なる市民”。今ある現実の中で楽しく生きることが好きだが、けっして愚かではなく、“異端者”を理解する自覚的な精神も持つ。けれども、権力に対して声高に批判はせず、夢は持ちつつも大きな波風の立たない人生を送りたいと願う人々。それが、グリンダ(ガリンダ)の本質だ。この物語の中でも、グリンダ(ガリンダ)は、“異端者”エルファバと、彼女を追いつめていく社会(権力者+煽動される国民)との間で揺れ動く。初めはエルファバをからかう側にいて、やがてエルファバの味方になるが、かと言って、危険を冒してまで彼女と共に過激な行動はできない。
そんな曖昧さがつきまとうグリンダ(ガリンダ)に、観客たちの多くは自分に近しいものを感じて感情移入する。観客は、自分もグリンダ(ガリンダ)に似て、過激ではないが“善良”であるはずだと思う。グリンダ(ガリンダ)がこれ見よがしの正義漢でないだけに、よけいそう思う。そのグリンダ(ガリンダ)を愛嬌たっぷりに演じるチェノウェスに、だから観客は大きな拍手を送る。それは、チェノウェスの演技に対する拍手であると同時に、グリンダ(ガリンダ)の曖昧さを愛すべきものとして受け入れられることを喜ぶ拍手でもある。つまり観客は、チェノウェス演じるグリンダ(ガリンダ)に魅力を覚えることで、無意識の内に“善良なる市民”である自分を許しているのだ。グリンダ(ガリンダ)が大きな役になるのは、そんな理由からだ。
チェノウェスが、そんなグリンダ(ガリンダ)にも哀しみがあることを忘れずに見事に表現していることも、観客にとっては大きな救いだろう。大詰め、手を取り合ってオズの国を(舞台奥に向かって)去っていくエルファバとフィエーロに視線を向けることなく、国民と共に“悪い西の魔女”の死を祝うグリンダの笑顔の裏の哀しみは、実は最も孤独なのは彼女であることを告げている。そんな健気さも、観客にとってはカタルシスのはずだ。
しかし、一方で、グリンダ(ガリンダ)の哀しみは、世界がけっして素晴らしくはないことに対する哀しみでもあるのだが……。
そんなわけで、クリスティン・チェノウェス、とにかくうまい。歌の表現力、声そのものの素晴らしさ、演技の表現力、いずれも文句のつけようがない。トニー賞主演女優賞確実、と言いたいところだが、ドナ・マーフィ(『Wonderful Town』)がいるからな。熾烈な争いになるでしょう。
一方のイディーナ・メンゼルは、屈折した背景を持ち直情的というエルファバのキャラクターが『Rent』のモリーンに酷似していて、歌、演技共に彼女にピッタリ。だからこその起用なのだろうが、全編を通して迫力いっぱいに歌うタイプの楽曲が多いのは、彼女にとっても観客にとっても、もったいなかった。ことに第2幕は、装置の転換の時間稼ぎなのではないかと思うのだが、立て続けにそのタイプの楽曲を歌っていて、いささか飽きる。魅力のある人だけに、芸の幅を広げて(あるいは深めて)、また驚かせてほしい。
逆に、ジョエル・グレイはいつものジョエル・グレイであるところが素晴らしい。今回はやや役不足(くどいようだが、役者の力量に対して役が物足りないこと)の感なきにもあらずだが、それでも、ただの気の弱い老人ではなく、魔法使い役の得体の知れなさを感じさせるあたり、さすが。
モリブル夫人役はキャロル・シェリー。こういう嫌らしい役をさりげなく演じられる人がいると、舞台が締まる。
ところで、問題は、フィエーロ役。オリジナル・キャストは『Thou Shalt Not』のカミーユ役で名を挙げたノーバート・レオ・バッツで、歌はもちろんうまいのだが、役柄として、自信家なのはいいのだが、どこかのほほんとしているという部分が、うまく出ていないように思えた。それが、今回、バッツの休暇を埋める長期の代役として登場していた『Rent』組の1人(ベニー役)テイ・ディグズを観たら、とてもしっくりきた。このまま彼がやった方がいいんじゃないだろうか。メンゼルとは夫婦だし……って、関係ないか(笑)。
演出はジョー・マンテロ。
ウェイン・シレントの振付は、ダンスだけを見せるシーンが少ないので目立たないが、転換時なども含めて注意して観ていると、かなり力の入った仕上がり。持ち味のキレのよさを充分に発揮して、けっこうダンサー泣かせかも。しかし、アンサンブルも高い要求によく応えている。
舞台上方にある大きなブリキ製のドラゴンが幕が開く前から目を惹くが、魔女が箒で空に舞いあがったり、猿が空を飛んだり、というケレンも生かしながらの、全編を通して工夫を凝らした大掛かりな装置はユージン・リー。ケネス・ポスナーの照明、スーザン・ヒルファティのカラフルな衣装とあいまって、不思議なオズ世界をスペクタクルに表現していて、観応えがある。そう言えば、猿やヤギの教師の扮装も凝っているし、視覚的には、とにかく贅沢だ。
それが、ユニヴァーサル映画がプロデューサーであることと関係があるのかどうかはわからないが、特殊効果を駆使した映像化を考えているとしてもおかしくない気はする。
今シーズンいちばんの大作であることは間違いない。>
“The Chronicle of Broadway and me #348(Wicked/Wicked[2])” への43件のフィードバック